健康コラム
2021.03.23

最近は、外食を控えてご自宅でお料理される頻度も増えたのではないでしょうか?
先月は、食材や加工食品に含まれる脂質について解説しましたが、今月は料理に使う「油」についてお話したいと思います。
2015年頃から、スーパーの調理油コーナーにはたくさんの種類の「油」が並ぶようになりました。
さて、油によってどのような調理方法に使い分ければいいでしょうか?
今までお話してきた脂肪酸の特徴から考えてみましょう。固まりやすい油、酸化されやすい油、香りの立つ油、無味無臭の油など、脂肪酸によって「油」の性状は異なります。
炒め物や揚げ物などの加熱調理には、酸化されにくい飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸を多く含む動物性油脂(バター、ラード)やオリーブ油、米油がおすすめです。
調理方法は、蒸し焼きした食材の最後の仕上げに油を回し入れて絡めたり、少量の油で揚げ焼きすることがおすすめです。そうすることで、脂質の摂取量や、酸化した揚げ油の使いまわしが減らせます。飽和度の高い油の方がカラッと仕上がります。
ごま油や落花生油などの油も、最後の仕上げにかける程度がよいですね。オメガ6系脂肪酸の摂取量を抑えながら、香りを楽しめます。
積極的に摂って欲しいオメガ3系脂肪酸は、長時間の加熱に弱く酸化されやすいのが最大の難点です。加熱調理油として使うよりも、酸味や香辛料などのスパイスを加えてドレッシングとして食材にかける、または味付けなしでそのまま料理にかけて召し上がるのもいいですね。目安量は1日小さじ1杯です。加熱に弱いといっても、温かいお味噌汁やお料理にかける程度の熱なら酸化を気にする必要はありません。
最近、脂質(脂味)は5つの基本味(甘味、塩味、酸味、苦味、旨味)に加え、「脂味」として認知されるほどで、脂肪分が増すと何でもコクが出ておいしく感じます。1日の脂質摂取量を超えない程度で、それぞれの「油」の利点を考えながら、お気に入りの調理方法を試されてみてはいかがでしょうか?
◆あぶら博士プロフィール
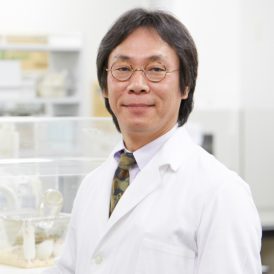
*守口 徹 先生(薬学博士)
麻布大学 生命・環境科学部 教授
日本脂質栄養学会 理事長
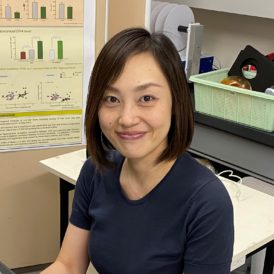
*原馬 明子 先生
麻布大学 生命・環境科学部 特任准教授
※文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。





